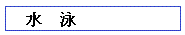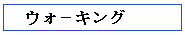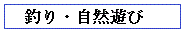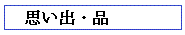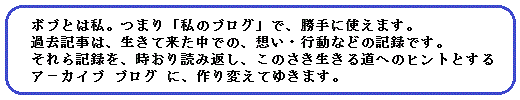
2011年7月に「ボブのブログ」をスタ-トさせ、1年後にア-カイブ ブログへの転用を考えました。
過去記事を月単位で読み返し、取捨選択を行い、保存の記事を最新24ヶ月以内に納めさせます。
新規記事も時おり加え、ア-カイブ内容の充実を、続けて行くつもりです。
ホトケノザ(野草)
2025年03月29日
東日本大震災が起きた2011年の11月、我が家の前の家に住んでいた一人暮らしの S さん が
急逝されました。
S さん の不動産は、一人娘の H さん が相続しましたが、彼女は日本に住んでおらず、それ以来
空き家となり、14年間 放置が続きました。
14年の間、この空き家での様々な問題が起き、放置しておくと見苦しいのと、2次被害も考えられ、その都度 無償で対処してきました。
庭木の剪定、雑草取り・害虫発生・落ち葉、枯草片付け・猫の糞尿問題・門扉倒れ・外観問題・
その他と、まさに空き家問題のオンパレ-ドでした。
昨年、来日のH さんが相続不動産を住宅業者に売却し、11月に住宅業者の取り壊しにより、空き家問題 は解消しました。
今は、日当たりが良い50坪ほどの更地に、一面に生えてきた ホトケノザ(シソ科)が紫の花を
付け、目を楽しませてくれています。
不思議に思うのが、何故今年に沢山の ホトケノザ(シソ科) が群生してきたのか?という事です。
14年間の雑草取りでは、一度も ホトケノザ(シソ科) で手を煩わされた事は無く、日当たりの良く
なった更地には、他の雑草が競って生えてきても当然な事なのに、何故 ホトケノザ(シソ科) だけなのか?と思います。
温厚だった S さん(享年73歳) が「長い間、お手数を掛けました。 ホトケノザの花 は、お礼の
気持ちからです。」 と、あの世から伝えているのかも知れません。
〈 ホトケノザ(シソ科) 〉 〈 我が家の前 一面に ホトケノザの花 〉


急逝されました。
S さん の不動産は、一人娘の H さん が相続しましたが、彼女は日本に住んでおらず、それ以来
空き家となり、14年間 放置が続きました。
14年の間、この空き家での様々な問題が起き、放置しておくと見苦しいのと、2次被害も考えられ、その都度 無償で対処してきました。
庭木の剪定、雑草取り・害虫発生・落ち葉、枯草片付け・猫の糞尿問題・門扉倒れ・外観問題・
その他と、まさに空き家問題のオンパレ-ドでした。
昨年、来日のH さんが相続不動産を住宅業者に売却し、11月に住宅業者の取り壊しにより、空き家問題 は解消しました。
今は、日当たりが良い50坪ほどの更地に、一面に生えてきた ホトケノザ(シソ科)が紫の花を
付け、目を楽しませてくれています。
不思議に思うのが、何故今年に沢山の ホトケノザ(シソ科) が群生してきたのか?という事です。
14年間の雑草取りでは、一度も ホトケノザ(シソ科) で手を煩わされた事は無く、日当たりの良く
なった更地には、他の雑草が競って生えてきても当然な事なのに、何故 ホトケノザ(シソ科) だけなのか?と思います。
温厚だった S さん(享年73歳) が「長い間、お手数を掛けました。 ホトケノザの花 は、お礼の
気持ちからです。」 と、あの世から伝えているのかも知れません。
〈 ホトケノザ(シソ科) 〉 〈 我が家の前 一面に ホトケノザの花 〉
お接待 歩き遍路回想
2025年03月15日
ア-カイブ記事 公開 : 2014年3月21日
四国の人達が行うお遍路さんへの接待は、同行二人で共に歩く お大師さんに施しをさせてもらう気持ちから で、お接待の良い行為は、やがて自分に戻ってくるとの信仰から行わていると、知った。
昨年の四国あるき遍路の中で、私は様々な物・形のお接待を受けて、お接待文化を実体験した。
最も多いお接待は、遍路道を歩いていると、その土地の人が「お接待をさせて下さい。」、または
「お接待です。」と言い、飲み物・食べ物を差し出すものだった。
中には、急に家から飛び出して、お接待をしてくれる人もいて、まるでお遍路が通るのを待ち構えて
いたかのように思えた。
思い出すままに、受けたお接待を並べると;
①.お遍路宿
・宿に着くと、金剛杖 を洗ってくれた。(これは、お大師さまの足を洗って差し上げる行為。)
・洗濯機/乾燥機を、無料で使わせてくれた。(ふつう、コインで300円かかった。)
・翌日、朝の出発時におにぎり弁当を、「お接待です。」と、無料提供してくれた。
・進路/次の泊まり宿等への、親切な情報を与えてくれた。
②.ビジネスホテル
・料金は同じで、1ランク上の部屋に泊めてくれた。
・あるホテルでは、「消費税分を、お接待します。」と、割り引いてくれた。
③.お接待小屋/遍路小屋
・ある地区や個人が、お遍路への休憩所を設けてくれ、水・果物・アメなどが置かれていた。
・39番延光寺に向かう芳井のお接待小屋には、冷蔵庫や熱いコ-ヒ-・湯の入ったポットが置いて
あり、冷たい飲み物/熱い飲み物/カップラ-メン/果物/菓子など、お遍路は好きなものを
自由に飲食出来た。
④.車に乗せるお接待
・長い上り坂を歩いていたら、ダンプカ-が止まり、「お遍路さん、乗ってゆきなよ。」と、言ってくれた。
・11月3日、寒い向かい風の中を、52番太山寺に向かって歩いていると、通り過ぎた軽自動車が
止まり、若く優しい女性が降りて来て、「お遍路さん、太山寺までお乗せします。」と、言ってくれた。
*礼を言い、「私は、乗り物を一切使わない歩き遍路を行っています。」と、両方とも断っている。
⑤.トイレのお接待
・遍路道にトイレがない土地で、「お遍路さん、お使い下さい。」の貼り紙で、工場等が従業員用の
トイレを解放していた。
⑥.コンビニストアのお接待
・高知のコンビニ「スリ-エフ」は、買い物をすると150円のペットボトル茶を、お接待してくれた。
・高知中の「スリ-エフ」は、皆同じに行い、160円のアイスを買っただけで、1本のお接待を受けた。
⑦.食べ物/飲み物のお接待
・遍路道を歩いていると、土地の人から果物/アメ/缶コ-ヒ-などを、お接待された。
・10月下旬に入ると、ミカン/柿のお接待が多くなり、1ヶ月でミカンは3年分ほど食べていた。
・11月12日、84番屋島寺に向かう途中、自転車ですれ違った若い女性が戻ってきて、「寒いので、
お昼に暖かい物を食べる足しにして下さい。」と、500円を差し出してくれた。
お金を受け取るのに抵抗を感じたが、お大師さんへの施しと考え直し、頂いた。
お礼を言ってから「南無大師遍照金剛」と唱え、屋島寺で彼女の幸せを祈願した。
⑧.記念品のお接待
・折り紙細工品/テイッシュ入れ/小さな焼き物の草履・お地蔵さんなど、お接待された。
・11月14日、88番大窪寺に着いたら、中年の男性から「83歳の母が作った人形です。どうか
お納め下さい。」と差し出された。 ご母堂は、あるき遍路結願の人に、上げるよう作っている
との由で、有り難く頂いた。
四国あるき遍路で受けたお接待の数々を思い出すと、各土地で善根を積む心豊かな人々との触れ
合いと施しのお蔭で、無事に四国一周を歩き通せたことが分かり、感謝の念が沸いてくる。
〈 83歳ご母堂手作りの人形、高さ5センチ 〉 〈お接待で頂いた記念品あれこれ 〉


*右写真の灰色のお地蔵さんは、77番道隆寺に向かう途中、家から飛び出してきた男性より「息子が作った、焼き物のお地蔵さんです。どうかお納め下さい。」と、頂いた。 お地蔵さんの体は、円空になっており、紙片が入っていた。 中央手前は、瓦の産地で有名な菊間町で頂いた焼物の草履。
四国の人達が行うお遍路さんへの接待は、同行二人で共に歩く お大師さんに施しをさせてもらう気持ちから で、お接待の良い行為は、やがて自分に戻ってくるとの信仰から行わていると、知った。
昨年の四国あるき遍路の中で、私は様々な物・形のお接待を受けて、お接待文化を実体験した。
最も多いお接待は、遍路道を歩いていると、その土地の人が「お接待をさせて下さい。」、または
「お接待です。」と言い、飲み物・食べ物を差し出すものだった。
中には、急に家から飛び出して、お接待をしてくれる人もいて、まるでお遍路が通るのを待ち構えて
いたかのように思えた。
思い出すままに、受けたお接待を並べると;
①.お遍路宿
・宿に着くと、金剛杖 を洗ってくれた。(これは、お大師さまの足を洗って差し上げる行為。)
・洗濯機/乾燥機を、無料で使わせてくれた。(ふつう、コインで300円かかった。)
・翌日、朝の出発時におにぎり弁当を、「お接待です。」と、無料提供してくれた。
・進路/次の泊まり宿等への、親切な情報を与えてくれた。
②.ビジネスホテル
・料金は同じで、1ランク上の部屋に泊めてくれた。
・あるホテルでは、「消費税分を、お接待します。」と、割り引いてくれた。
③.お接待小屋/遍路小屋
・ある地区や個人が、お遍路への休憩所を設けてくれ、水・果物・アメなどが置かれていた。
・39番延光寺に向かう芳井のお接待小屋には、冷蔵庫や熱いコ-ヒ-・湯の入ったポットが置いて
あり、冷たい飲み物/熱い飲み物/カップラ-メン/果物/菓子など、お遍路は好きなものを
自由に飲食出来た。
④.車に乗せるお接待
・長い上り坂を歩いていたら、ダンプカ-が止まり、「お遍路さん、乗ってゆきなよ。」と、言ってくれた。
・11月3日、寒い向かい風の中を、52番太山寺に向かって歩いていると、通り過ぎた軽自動車が
止まり、若く優しい女性が降りて来て、「お遍路さん、太山寺までお乗せします。」と、言ってくれた。
*礼を言い、「私は、乗り物を一切使わない歩き遍路を行っています。」と、両方とも断っている。
⑤.トイレのお接待
・遍路道にトイレがない土地で、「お遍路さん、お使い下さい。」の貼り紙で、工場等が従業員用の
トイレを解放していた。
⑥.コンビニストアのお接待
・高知のコンビニ「スリ-エフ」は、買い物をすると150円のペットボトル茶を、お接待してくれた。
・高知中の「スリ-エフ」は、皆同じに行い、160円のアイスを買っただけで、1本のお接待を受けた。
⑦.食べ物/飲み物のお接待
・遍路道を歩いていると、土地の人から果物/アメ/缶コ-ヒ-などを、お接待された。
・10月下旬に入ると、ミカン/柿のお接待が多くなり、1ヶ月でミカンは3年分ほど食べていた。
・11月12日、84番屋島寺に向かう途中、自転車ですれ違った若い女性が戻ってきて、「寒いので、
お昼に暖かい物を食べる足しにして下さい。」と、500円を差し出してくれた。
お金を受け取るのに抵抗を感じたが、お大師さんへの施しと考え直し、頂いた。
お礼を言ってから「南無大師遍照金剛」と唱え、屋島寺で彼女の幸せを祈願した。
⑧.記念品のお接待
・折り紙細工品/テイッシュ入れ/小さな焼き物の草履・お地蔵さんなど、お接待された。
・11月14日、88番大窪寺に着いたら、中年の男性から「83歳の母が作った人形です。どうか
お納め下さい。」と差し出された。 ご母堂は、あるき遍路結願の人に、上げるよう作っている
との由で、有り難く頂いた。
四国あるき遍路で受けたお接待の数々を思い出すと、各土地で善根を積む心豊かな人々との触れ
合いと施しのお蔭で、無事に四国一周を歩き通せたことが分かり、感謝の念が沸いてくる。
〈 83歳ご母堂手作りの人形、高さ5センチ 〉 〈お接待で頂いた記念品あれこれ 〉
*右写真の灰色のお地蔵さんは、77番道隆寺に向かう途中、家から飛び出してきた男性より「息子が作った、焼き物のお地蔵さんです。どうかお納め下さい。」と、頂いた。 お地蔵さんの体は、円空になっており、紙片が入っていた。 中央手前は、瓦の産地で有名な菊間町で頂いた焼物の草履。
寝泊まり 歩き遍路回想
2025年03月11日
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月22日
四国八十八ヶ所霊場を歩きのみで巡る旅 を行った私にとって、歩いた日の疲れを取る寝泊りは、
最も重要だった。 良い寝泊りが得られると、翌朝は元気を取り戻せており、その日に訪れる札所に向け、気持ち良く歩き出せていた。
寝泊りの方法として、①.野宿 ②.宿などへの泊りがあり、今でも野宿を組込みながら、歩き遍路を
続けている人達がいた。 野宿は、季節により暑さ・寒さ・蚊などの問題で良く眠れない辛さと、
食事・衛生などへの準備をすれば、炊飯具・寝袋などの持参が必要となり、リュックの重さが増え、
日中に歩く時のハンデとなって大変なことだ。
しかし、苦労は修業の一つとして、野宿を入れながら四国遍路を行う人に、何度か出合ってもいる。
今回の四国歩き遍路で、私が45泊した寝泊り宿は、成り行きで次のようになった。
①.遍路宿 11泊 … 札所を巡る遍路道に沿って在り、お遍路にとって最適の宿。減少していた。
1泊2食料金-- 5000~6000円
②.宿 坊 1泊 … 札所の寺が、お遍路を泊める設備。宿坊を持つ寺は、4分の1くらいか?
金剛頂寺 では、1泊2食料金 -- 6000円
*素晴らしい設備・美味しい豪華な食事・親切な対応で、大満足。
③.一般民宿 12泊 … 一般客が使う民宿で、サ-ビス内容にレベル差があった。
1泊2食料金 -- 5500~6500円
④.旅 館 13泊 … 観光地や、JR の駅近くなどにあった旅館。 温泉地も含まれる。
1泊2食料金 -- 6500~8500円
*①.~④.素泊まり -- 3000~4000円
⑤.ビジネスホテル 8泊 … 高知・宇和島・高松など大きな都市の駅近辺で、利用出来た。
1泊朝食料金 -- 4000~5500円
⑥.無料宿泊所 1泊 … 野宿者や、宿を取れない遍路者に提供される施設(善根宿)。
歩き遍路者へのバイブル地図本「四国遍路ひとり歩き同行二人」を知らず、全旅程の3分の2を
この地図本無しで歩き、寝泊りへの宿の確保にかなり苦労し、上記の結果となった。
 普段生活で、夜になれば何も考えずに寝床に就いていたが、あるき遍路に出て、寝泊りする場の有り難さ・寝泊りの大切さを、認識させられた。
普段生活で、夜になれば何も考えずに寝床に就いていたが、あるき遍路に出て、寝泊りする場の有り難さ・寝泊りの大切さを、認識させられた。
原発事故で避難し不便な生活を強いられている人々・
人生の歯車が狂いホ-ムレスで路上生活をせざるを
得ない人達など、かっての眠りの場から離され、厳しい
冬の寒さに向かっている。
何もして上げられないが、それらの人々が、少しづつでも良い方向に向かえるよう、お祈りしたい。
四国八十八ヶ所霊場を歩きのみで巡る旅 を行った私にとって、歩いた日の疲れを取る寝泊りは、
最も重要だった。 良い寝泊りが得られると、翌朝は元気を取り戻せており、その日に訪れる札所に向け、気持ち良く歩き出せていた。
寝泊りの方法として、①.野宿 ②.宿などへの泊りがあり、今でも野宿を組込みながら、歩き遍路を
続けている人達がいた。 野宿は、季節により暑さ・寒さ・蚊などの問題で良く眠れない辛さと、
食事・衛生などへの準備をすれば、炊飯具・寝袋などの持参が必要となり、リュックの重さが増え、
日中に歩く時のハンデとなって大変なことだ。
しかし、苦労は修業の一つとして、野宿を入れながら四国遍路を行う人に、何度か出合ってもいる。
今回の四国歩き遍路で、私が45泊した寝泊り宿は、成り行きで次のようになった。
①.遍路宿 11泊 … 札所を巡る遍路道に沿って在り、お遍路にとって最適の宿。減少していた。
1泊2食料金-- 5000~6000円
②.宿 坊 1泊 … 札所の寺が、お遍路を泊める設備。宿坊を持つ寺は、4分の1くらいか?
金剛頂寺 では、1泊2食料金 -- 6000円
*素晴らしい設備・美味しい豪華な食事・親切な対応で、大満足。
③.一般民宿 12泊 … 一般客が使う民宿で、サ-ビス内容にレベル差があった。
1泊2食料金 -- 5500~6500円
④.旅 館 13泊 … 観光地や、JR の駅近くなどにあった旅館。 温泉地も含まれる。
1泊2食料金 -- 6500~8500円
*①.~④.素泊まり -- 3000~4000円
⑤.ビジネスホテル 8泊 … 高知・宇和島・高松など大きな都市の駅近辺で、利用出来た。
1泊朝食料金 -- 4000~5500円
⑥.無料宿泊所 1泊 … 野宿者や、宿を取れない遍路者に提供される施設(善根宿)。
歩き遍路者へのバイブル地図本「四国遍路ひとり歩き同行二人」を知らず、全旅程の3分の2を
この地図本無しで歩き、寝泊りへの宿の確保にかなり苦労し、上記の結果となった。
原発事故で避難し不便な生活を強いられている人々・
人生の歯車が狂いホ-ムレスで路上生活をせざるを
得ない人達など、かっての眠りの場から離され、厳しい
冬の寒さに向かっている。
何もして上げられないが、それらの人々が、少しづつでも良い方向に向かえるよう、お祈りしたい。
歩き遍路 ヘンロ小屋
2025年03月07日
ア-カイブ記事 公開 : 2014年2月25日
昨年10~11月の通し打ち歩き遍路では、12Kgの荷を背負って、毎日30Km以上を歩いていた。
朝7時頃に宿を立ち、夕方5時頃に次の宿に入るまでの間に、休憩を適度に取るよう心掛けた。
約90分歩いて10分ほどの休憩と、昼食を取りながらの休憩を基本とし、これらの休憩時にリュックを下ろし座れる場所が見つかると、体を休める事が出来、有り難かった。
座れて休憩出来る場所として、①.篤志家提供の休憩場所 ②.四国八十八ヶ所 ヘンロ小屋プロ
ジェクトで建てられたヘンロ小屋 ③.お寺(札所)境内のベンチ ④.駅の道の休み処 などが
あった。
これらの中で、一番よく利用出来たのが、ヘンロ小屋プロジェクトで出来たヘンロ小屋で、次の札所に向かって歩いて行き、疲労を覚え出した頃の位置に在って、具合よく体を休めることが出来た。
休憩・仮眠出来る小屋の建設プロジェクトを立ち上げ、
敷地提供・木材提供・建設協力・資金寄付など多くの人々から協力を得て、四国八十八ヶ所一円に、ヘンロ小屋建設を推進している。
立ち寄ったヘンロ小屋のそれぞれは、各小屋がテ-マを持ったデザイン・設計らしく、皆異なった姿恰好をしており
目も楽しませてくれた。
炎天下を延々と歩き続け、汗だくになったお遍路にとって、屋根の日除けがあり風通しのよい構造の小屋は、遍路のオアシスだった。
右の写真の日は、激しい雷雨に遭った日で、次々と歩き
遍路者が、この小屋に飛び込んで来て、雨が小降りになるのを待った。この小屋が無ければ、雨宿りを出来ずに歩き続けるより仕方なく、有り難さをより感じた日だった。
写真の方は、このヘンロ小屋への敷地を提供した農家のサダさん。 スダチの収穫も終わり、87歳のサダさんは
この小屋でお遍路と話をするのが、楽しみだそうだ。
お元気で、目が生き生きとしており、話もしっかりとされ、
私はついつい30分も話をしていた。
「記念に写真を、撮らせて下さい。」と言ったら、手拭被りを外して、私の金剛杖を持ち、にっこりと
笑って下さった。 可愛いサダさん、お元気で長生きして下さい。
追記 : 今日(11月6日)は雲一つない晴天で、空を見つめましたら、8年前の11月は 四国遍路
あるき旅 の真っ最中だったことを、思い出しました。
歩きの途中で、休ませてもらったサダさんのヘンロ小屋。 今もお元気と思いますサダさん、
毎日 お遍路さんとお話をされていることでしょう。
道しるべ 歩き遍路回想
2025年02月21日
ア-カイブ記事 公開 : 2013年1月30日
道しるべ(道標) … 目的地までの方向や、距離をしるした立札・石碑など。道案内。
初めての四国歩き遍路に、不十分な地図・情報しか持たなかった私は、12番焼山寺を過ぎてから、道に迷う難儀が起き始めていた。
7日目に泊まった宿で、歩き遍路は地図本「四国遍路ひとり歩き同行二人」の携帯なしでは、歩き
続けるのは無理と云われ、一刻も早く入手するようアドバイスを受けた。
その地図本を見せてもらうと、必要な情報が全て載っており納得したが、この地図本を入手出来た
のは、26日後の54番延命寺の売店だった。
この地図本を入手してからは、道に迷うことは少なくなり、宿の予約が楽に出来るようになった。
全行程の3分の2を、バイブル地図本 なしで、なんとか54番延命寺に辿り着いたものだが、それは
遍路道の要所・分岐点にある道しるべのお蔭 だった。
遍路道で出会った道しるべは、大きく三つに分けられた。
1.へんろ道保存協力会の道しるべ 宮崎建樹さんが、赤矢印・赤お遍路姿など分かりやすい
マ-クを考案され、遍路道の整備目的で、個人の労力・資金によって設置し始めたもの。
道しるべとしてへんろシ-ル・道しるべ札・立札が使われ、遍路道の分岐点に貼られたり
設置されており、今の時代のお遍路はこれらの道しるべを頼りに、次の札所へと歩いて行く。
〈 曲がり角の道しるべ札 〉 〈 まっすぐ進めの道しるべ 〉


2.昔の道しるべ… 江戸時代から残る石碑で、人指し指が浮き彫りされ、方向を教えている。
旧遍路道に残った昔の石碑道しるべに出会うと、昔のお遍路と同じ道を歩いている感慨が湧いた。
〈 手間を掛けた浮き彫り石碑 〉 〈 風雪で字がかすれた石碑 〉


3.現代の道しるべ … 国道の道路標識。四国のみち の道しるべ(石碑、木。)など。
 ・国道を歩く時に頼りにしたのが、道路標識。
・国道を歩く時に頼りにしたのが、道路標識。
幹線道路から離れると、地名標識は極端に少ない。
・四国を一周する四国のみち は、国土交通省四国が
設置した最近の道しるべで、石碑・木製の両方が
あり見易かった。
都市部を離れると、地名表示は少なく、誰かに訊きたくても、人影が見当たらないことが多かった。
その様な時、道しるべだけが頼りとなるが、貼られた小さなへんろシ-ルを見逃してしまったり、
余所者が迷いそうな場所なのに、道しるべは無かったりして、道に迷うことが多々起きた。
逆に、都市部に入ると、1.の道しるべ が無い事が多く、余計な道歩き修業?をさせられた。
*教訓 「いつまでもあると思うな、親と金。」 → 「 いつまでもあると思うな、道しるべ。」
道しるべ(道標) … 目的地までの方向や、距離をしるした立札・石碑など。道案内。
初めての四国歩き遍路に、不十分な地図・情報しか持たなかった私は、12番焼山寺を過ぎてから、道に迷う難儀が起き始めていた。
7日目に泊まった宿で、歩き遍路は地図本「四国遍路ひとり歩き同行二人」の携帯なしでは、歩き
続けるのは無理と云われ、一刻も早く入手するようアドバイスを受けた。
その地図本を見せてもらうと、必要な情報が全て載っており納得したが、この地図本を入手出来た
のは、26日後の54番延命寺の売店だった。
この地図本を入手してからは、道に迷うことは少なくなり、宿の予約が楽に出来るようになった。
全行程の3分の2を、バイブル地図本 なしで、なんとか54番延命寺に辿り着いたものだが、それは
遍路道の要所・分岐点にある道しるべのお蔭 だった。
遍路道で出会った道しるべは、大きく三つに分けられた。
1.へんろ道保存協力会の道しるべ 宮崎建樹さんが、赤矢印・赤お遍路姿など分かりやすい
マ-クを考案され、遍路道の整備目的で、個人の労力・資金によって設置し始めたもの。
道しるべとしてへんろシ-ル・道しるべ札・立札が使われ、遍路道の分岐点に貼られたり
設置されており、今の時代のお遍路はこれらの道しるべを頼りに、次の札所へと歩いて行く。
〈 曲がり角の道しるべ札 〉 〈 まっすぐ進めの道しるべ 〉
2.昔の道しるべ… 江戸時代から残る石碑で、人指し指が浮き彫りされ、方向を教えている。
旧遍路道に残った昔の石碑道しるべに出会うと、昔のお遍路と同じ道を歩いている感慨が湧いた。
〈 手間を掛けた浮き彫り石碑 〉 〈 風雪で字がかすれた石碑 〉
3.現代の道しるべ … 国道の道路標識。四国のみち の道しるべ(石碑、木。)など。
幹線道路から離れると、地名標識は極端に少ない。
・四国を一周する四国のみち は、国土交通省四国が
設置した最近の道しるべで、石碑・木製の両方が
あり見易かった。
都市部を離れると、地名表示は少なく、誰かに訊きたくても、人影が見当たらないことが多かった。
その様な時、道しるべだけが頼りとなるが、貼られた小さなへんろシ-ルを見逃してしまったり、
余所者が迷いそうな場所なのに、道しるべは無かったりして、道に迷うことが多々起きた。
逆に、都市部に入ると、1.の道しるべ が無い事が多く、余計な道歩き修業?をさせられた。
*教訓 「いつまでもあると思うな、親と金。」 → 「 いつまでもあると思うな、道しるべ。」
歩く 歩き遍路回想
2025年02月16日
ア-カイブ記事 公開 : 2013年1月16日
歩く事が健康に良いとの確信を、ボブのブログ 公開記事「歩かねば」で書いている。
歩く事で精神を鍛えるのは、四国遍路の1,400Kmを歩き通す歩行行(ほこうぎょう)がその例で、
NHKラジオ講座 “ 四国遍路を考える ” では、「歩き通す事と云う苦行 を設定し、それに挑戦し、
人間の可能性を追求して行く。」と、語られていた。
さらに、「人生とは生きること。挑戦の連続。」・「道は、人生。」・「歩くは、生きる。」・「今まで生きて
きた過去の人生は、今まで歩いて来た道。 これからの人生に、どのような道を選ぶか?どのように歩くか?は、本人の心掛けで決まる。」などとも云われている。
しかし、私の四国あるき遍路は、そのような考えや目的を持たず、(人が行っている事を、真似して
やってみよう。)の軽い気持ちを主として、始めたものだった。
鳴門がスタ-ト点で、計九十九ヶ所の札所を、交通機関を一切使わずに、道に迷うなどしながらも、
45日間で1,480Kmを歩き通し終える事が出来、46日目には高野山奥の院にお礼詣りも行えた。
実際に歩いた道は、昔の人が遍路で歩いた旧遍路道・車社会になって出来た遍路道・国道・トンネル道・一般道・農道・田のあぜ道・山中で迷い歩いた獣道など様々だった。
歩いた様々な道の中で、思い出に残る道は旧遍路道だが、特に山間部にある険しい修験道として
使われた古道だった。 そのような道は、12番焼山寺に向かう「へんろ転がし」や、27番神峰寺の
「真っ縦」等など何ヶ所もあって、山の精霊を感じるほど静寂な中、滅多に人とも合わずに金剛杖を
頼りに、修業を頭に浮かべながら歩いていた。
喘ぎ喘ぎ大汗をかきながら登り下りと歩く道がほとんどで、12Kgのリュックを重く肩に感じ、捨てればどれだけ楽になるだろうと思い、立ち止まりながら、歩くのはもう嫌だの考えが、頭を占めて来る。
しかし、険しい山道には車は入れず、他人に頼ることも出来ない場所であり、自分から足を動かさ
ないかぎり、晩の食事・寝床が得られない事は明白だった。 この修験道では、如何に苦しく辛く
とも、自ら歩かねば生きるに繋がらない事を、教えられていた。
「歩くは、生きること。」と、遍路で長く続く道を「歩かねば!」と、一歩一歩 踏み出していった。


歩く事が健康に良いとの確信を、ボブのブログ 公開記事「歩かねば」で書いている。
歩く事で精神を鍛えるのは、四国遍路の1,400Kmを歩き通す歩行行(ほこうぎょう)がその例で、
NHKラジオ講座 “ 四国遍路を考える ” では、「歩き通す事と云う苦行 を設定し、それに挑戦し、
人間の可能性を追求して行く。」と、語られていた。
さらに、「人生とは生きること。挑戦の連続。」・「道は、人生。」・「歩くは、生きる。」・「今まで生きて
きた過去の人生は、今まで歩いて来た道。 これからの人生に、どのような道を選ぶか?どのように歩くか?は、本人の心掛けで決まる。」などとも云われている。
しかし、私の四国あるき遍路は、そのような考えや目的を持たず、(人が行っている事を、真似して
やってみよう。)の軽い気持ちを主として、始めたものだった。
鳴門がスタ-ト点で、計九十九ヶ所の札所を、交通機関を一切使わずに、道に迷うなどしながらも、
45日間で1,480Kmを歩き通し終える事が出来、46日目には高野山奥の院にお礼詣りも行えた。
実際に歩いた道は、昔の人が遍路で歩いた旧遍路道・車社会になって出来た遍路道・国道・トンネル道・一般道・農道・田のあぜ道・山中で迷い歩いた獣道など様々だった。
歩いた様々な道の中で、思い出に残る道は旧遍路道だが、特に山間部にある険しい修験道として
使われた古道だった。 そのような道は、12番焼山寺に向かう「へんろ転がし」や、27番神峰寺の
「真っ縦」等など何ヶ所もあって、山の精霊を感じるほど静寂な中、滅多に人とも合わずに金剛杖を
頼りに、修業を頭に浮かべながら歩いていた。
喘ぎ喘ぎ大汗をかきながら登り下りと歩く道がほとんどで、12Kgのリュックを重く肩に感じ、捨てればどれだけ楽になるだろうと思い、立ち止まりながら、歩くのはもう嫌だの考えが、頭を占めて来る。
しかし、険しい山道には車は入れず、他人に頼ることも出来ない場所であり、自分から足を動かさ
ないかぎり、晩の食事・寝床が得られない事は明白だった。 この修験道では、如何に苦しく辛く
とも、自ら歩かねば生きるに繋がらない事を、教えられていた。
「歩くは、生きること。」と、遍路で長く続く道を「歩かねば!」と、一歩一歩 踏み出していった。
花ごよみ 二月
2025年02月10日
狭い庭を使い、季節を知らせる花が咲く草木をと心掛け、園芸の真似事をしてきました。
傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 二月 は、鉢植えの 日本水仙 を載せました。
2013年1月18日に、千葉県きょなん町保田地区で行われていた水仙まつり の見物に出掛け、
江月水仙ロードで群生する日本水仙を鑑賞してきました。
その時、土産として買った 日本水仙 の苗を大き目の鉢植えにしたものが、連綿と生き続け
今の時期に清楚な姿に可憐な花を付け、芳香も漂わせてくれています。

傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 二月 は、鉢植えの 日本水仙 を載せました。
2013年1月18日に、千葉県きょなん町保田地区で行われていた水仙まつり の見物に出掛け、
江月水仙ロードで群生する日本水仙を鑑賞してきました。
その時、土産として買った 日本水仙 の苗を大き目の鉢植えにしたものが、連綿と生き続け
今の時期に清楚な姿に可憐な花を付け、芳香も漂わせてくれています。
〈 芳香を放つ 日本水仙 の花 〉
花ごよみ 一月
2025年01月05日
狭い庭を使い、季節を知らせる花が咲く草木をと心掛け、園芸の真似事をしてきました。
傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
1月に咲いている花は ロウバイ です。
秩父の 宝登山のロウバイ見物 に行った際、土産に30センチほどの苗木を買い、庭に片隅に植え
ますと、しっかり根付き 毎年 花の少ない1月一杯 咲いてくれます。
*ボブのブログ 「 ロウバイは見頃です。 」
https://admin.tamaliver.jp/admin/entry/edit/entry_id/497848
〈 ロウバイの花 薄い蝋のような花弁 〉 〈 2メートルほどに育ったロウバイ 〉


傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
1月に咲いている花は ロウバイ です。
秩父の 宝登山のロウバイ見物 に行った際、土産に30センチほどの苗木を買い、庭に片隅に植え
ますと、しっかり根付き 毎年 花の少ない1月一杯 咲いてくれます。
*ボブのブログ 「 ロウバイは見頃です。 」
https://admin.tamaliver.jp/admin/entry/edit/entry_id/497848
〈 ロウバイの花 薄い蝋のような花弁 〉 〈 2メートルほどに育ったロウバイ 〉
時を刻む
2025年01月01日
新年を迎え、私が決まって行うのは、窓辺に飾ったこの置時計を動かす事です。
この時計は、古時計のご紹介 その1 で紹介
した、19世紀にフランスで製造されたものです。
高さ55センチ・幅33センチの大きさで、美しく大きなガラスのホヤを取り外し、ゼンマイを捲きます。
ゼンマイを一杯に捲くと、2週間は動き、長針が真上・真下に来ると、済んだ鐘の音で「チン・
チン・チン…」と鳴ります。
普段も動かしたいのですが、万が一ガラスのホヤを割ったりするのが怖く、お正月とハレの日だけ、
動かしています。
駐在で2年半 住んだオルレアンの蚤の市で、ホコリを被り動かなかった時計を見て買い求め、故障原因の部品を別の日に蚤の市で探しだし、分解掃除と調整の結果、150年以上過ぎた時計が、
今でも時を刻むのは嬉しいことです。
 置き時計のケースは、若い貴族が釣り上げた
置き時計のケースは、若い貴族が釣り上げた
魚を自慢げに持つポ-ズをしており、釣りを行う
私の趣味にあっています。
また、美しく大きなガラスのホヤ ・白磁の
文字盤+ブレゲ針・手作り捲きカギなどが
19世紀の時計として素晴らしく、大のお気に
入りです。
ゼンマイを一杯に捲くと、2週間も動き続けますが、ゼンマイが解けてくると、振り子の動きは
元気を失い、時間に狂いも出て来るのは、
歳を重ねるにつれて弱って行く人間のようにも
思えます。
新年を迎え、この時計を動かす時、私も更に老いの道を進んだ事を、自覚させられます。
「元旦や、冥土の旅の一里塚。 めでたくもあり、めでたくもなし。」
昨今は体力の衰えに気付き、フレイルも他人事でなくなってきました。
更にコロナ禍が続く時代、私の寿命が急に切れるかも知れませんが、この置時計はゴミとならず、
後世に伝わっていく事を願うものです。
〈 鍛造で手作りされた美しいカギ 〉

この時計は、古時計のご紹介 その1 で紹介
した、19世紀にフランスで製造されたものです。
高さ55センチ・幅33センチの大きさで、美しく大きなガラスのホヤを取り外し、ゼンマイを捲きます。
ゼンマイを一杯に捲くと、2週間は動き、長針が真上・真下に来ると、済んだ鐘の音で「チン・
チン・チン…」と鳴ります。
普段も動かしたいのですが、万が一ガラスのホヤを割ったりするのが怖く、お正月とハレの日だけ、
動かしています。
駐在で2年半 住んだオルレアンの蚤の市で、ホコリを被り動かなかった時計を見て買い求め、故障原因の部品を別の日に蚤の市で探しだし、分解掃除と調整の結果、150年以上過ぎた時計が、
今でも時を刻むのは嬉しいことです。
魚を自慢げに持つポ-ズをしており、釣りを行う
私の趣味にあっています。
また、美しく大きなガラスのホヤ ・白磁の
文字盤+ブレゲ針・手作り捲きカギなどが
19世紀の時計として素晴らしく、大のお気に
入りです。
ゼンマイを一杯に捲くと、2週間も動き続けますが、ゼンマイが解けてくると、振り子の動きは
元気を失い、時間に狂いも出て来るのは、
歳を重ねるにつれて弱って行く人間のようにも
思えます。
新年を迎え、この時計を動かす時、私も更に老いの道を進んだ事を、自覚させられます。
「元旦や、冥土の旅の一里塚。 めでたくもあり、めでたくもなし。」
昨今は体力の衰えに気付き、フレイルも他人事でなくなってきました。
更にコロナ禍が続く時代、私の寿命が急に切れるかも知れませんが、この置時計はゴミとならず、
後世に伝わっていく事を願うものです。
〈 鍛造で手作りされた美しいカギ 〉
花ごよみ 十二月
2024年12月26日
狭い庭を使い、季節を知らせる花が咲く草木をと心掛け、園芸の真似事をしてきました。
傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 十二月 は、 サザンカ です。
13年前に、終の棲家への家の建て替えを行いました。
元の家の取り壊しの際に、それまで狭い庭に植えてあった草木のすべても取り除かれました。
終の棲家が完成し、老い行く身に安心な住まいとなりましたが、何も植わって無い狭い庭は寂しく
ごろ石の混じった庭土の土振るいを行いながら、園芸プランを練りました。
建て替えの記念となり、花の少ない季節に咲く樹木は?と考え選んだのが サザンカ でした。
ホ-ムセンタ-で買い求め植えたサザンカは、毎年10月から咲き始め3ヶ月の間 次から次に花が咲き続いており、満足な選択でした。
〈 サザンカ 祖父江 〉 〈 木の高さは 1.5m 〉


傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 十二月 は、 サザンカ です。
13年前に、終の棲家への家の建て替えを行いました。
元の家の取り壊しの際に、それまで狭い庭に植えてあった草木のすべても取り除かれました。
終の棲家が完成し、老い行く身に安心な住まいとなりましたが、何も植わって無い狭い庭は寂しく
ごろ石の混じった庭土の土振るいを行いながら、園芸プランを練りました。
建て替えの記念となり、花の少ない季節に咲く樹木は?と考え選んだのが サザンカ でした。
ホ-ムセンタ-で買い求め植えたサザンカは、毎年10月から咲き始め3ヶ月の間 次から次に花が咲き続いており、満足な選択でした。
〈 サザンカ 祖父江 〉 〈 木の高さは 1.5m 〉
般若心経 歩き遍路回想
2024年12月13日
ア-カイブ記事 公開 : 2012年11月28日
初めて般若心経を聞いたのは、12年前に父が永眠し、遺骨がまだ家にある間に、親友のK氏が
訪れてくれ、焼香と読経をしてくれた時だった。
彼が般若心経をそらんじていた事に、少し驚いたが、心を込めて唱えられる般若心経を、有り難く
思いながら聴いた。 私も、般若心経を唱えられる様になりたいと思い、さっそく経文を入手し暗記を始め、覚える事が出来た。
般若心経を覚えた頃、NHK TV ドキュメント 柳沢桂子 般若心経について語る が放映された。
この番組を観て、柳沢桂子の生命科学者としての経歴、彼女を襲う難病との壮絶な闘い、その中で彼女が般若心経を翻訳し、『生きて死ぬ智慧』 として出版したことを知った。
さっそく、この本を買って読み、さらに般若心経を解釈する何冊かの他者の著書を読み、「空」の
理念が理解出来てくると、それまで抱いていた 死への戸惑い ・ 慄き が、心の中から消えていた。
それらの本の中で、四国札所巡礼のおりに、巡礼者は必ず般若心経を読経する習わしと知り、四国八十八ヶ所霊場巡礼に関心を持つようになった。
2010年4月~6月に、NHK ラジオ第2放送で「四国遍路を考える」(講師:真鍋俊照-- 四国霊場
第4番 大日寺住職・四国大学教授)が、13回にわたり放送され、欠かさず聞くことが出来た。
この講座から、四国遍路の歴史と世界を学び、元気な内に 四国あるき遍路を行ってみたい と
考え、実行したものだった。
〈 衛門三郎 と 弘法大師 〉
初めて般若心経を聞いたのは、12年前に父が永眠し、遺骨がまだ家にある間に、親友のK氏が
訪れてくれ、焼香と読経をしてくれた時だった。
彼が般若心経をそらんじていた事に、少し驚いたが、心を込めて唱えられる般若心経を、有り難く
思いながら聴いた。 私も、般若心経を唱えられる様になりたいと思い、さっそく経文を入手し暗記を始め、覚える事が出来た。
般若心経を覚えた頃、NHK TV ドキュメント 柳沢桂子 般若心経について語る が放映された。
この番組を観て、柳沢桂子の生命科学者としての経歴、彼女を襲う難病との壮絶な闘い、その中で彼女が般若心経を翻訳し、『生きて死ぬ智慧』 として出版したことを知った。
さっそく、この本を買って読み、さらに般若心経を解釈する何冊かの他者の著書を読み、「空」の
理念が理解出来てくると、それまで抱いていた 死への戸惑い ・ 慄き が、心の中から消えていた。
それらの本の中で、四国札所巡礼のおりに、巡礼者は必ず般若心経を読経する習わしと知り、四国八十八ヶ所霊場巡礼に関心を持つようになった。
2010年4月~6月に、NHK ラジオ第2放送で「四国遍路を考える」(講師:真鍋俊照-- 四国霊場
第4番 大日寺住職・四国大学教授)が、13回にわたり放送され、欠かさず聞くことが出来た。
この講座から、四国遍路の歴史と世界を学び、元気な内に 四国あるき遍路を行ってみたい と
考え、実行したものだった。
〈 衛門三郎 と 弘法大師 〉
金剛杖 歩き遍路回想
2024年12月02日
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月10日
第1番 霊山寺横の売店で、金剛杖・白衣(おいづる)・輪袈裟・菅笠・納経帳を買い、身につけると、一見で お遍路 と分かる姿となった。 金剛杖について学んだ事を、ここに書き残しておく。
1.遍路とお遍路
遍路とは、弘法大師(お大師様)が開いた四国八十八ヶ所霊場(札所)を巡拝(巡礼)することで、
巡拝する人が お遍路 と呼ばれ、地元の人は敬意と親しみを込め、お遍路さんと呼ぶ。
2.同行二人(どうぎょうににん)
買った金剛杖と菅笠には、同行二人と書かれており、これは遍路には お大師様がついて一緒に
歩いてくれている事を示し、特に金剛杖はお大師様の分身・化身と教えられた。
この教えは、一人で遍路道を歩いて行く私にとって、心強く感じられた。
お遍路を泊める宿の多くでは、お遍路が宿に辿り着くと「お杖を、洗いましょう。」と受け取り、清水で
洗い手拭で拭いたあとで返してくれる。 その金剛杖を泊まり部屋の中に持ち込み、床の間か部屋の一番良い場所に立てかけるように、言われた。
お杖を洗うのは、金剛杖をお大師様そのものと考え、遍路旅で汚れたに違いないお大師様の足を
洗って差し上げるものだった。
3.死出の旅
江戸時代に盛んになってきた四国遍路では、現代とは比較にならない厳しい歩き旅をするもので、
四国遍路は死出の旅と言われていた。
お大師様の救いを願って遍路に出た、病苦や悩み等を抱えた人もいて、それらの人達の中には遍路途中で行き倒れることも多くあったそうだ。
お遍路さんが遍路途中に亡くなると、その土地の人が、亡くなったお遍路さんを土に埋め、その上に金剛杖を立てたもので、金剛杖は墓標の役割も果たしたと言われている。
4.墓標代わり
五輪塔とは、死者へ対する供養や墓標として造られた石塔で、その形は「5大」を表した5種類の
パ-ツから出来ている。
金剛杖の頭部には、この「5大」が梵字で刻まれており、この部分は大切なものとして、直接手に触れないように錦布で包まれている。
昔の四国遍路では、行き倒れ亡くなったお遍路の金剛杖を、墓標として使っていたそうだ。
5.私の金剛杖
四国あるき遍路を、乗り物を一切使わず 45泊46日の通し で結願出来たのは、金剛杖にいつも
支えられていた気持ちのお蔭と、実感している。
四国遍路を結願し、第88番 大窪寺に金剛杖を納める人たちも居るそうだが、私は記念に家に持ち帰った。
あるガイドブックによると、死出の際に四国遍路に使った金剛杖を棺桶に入れてもらう と、その人は
浄土へ導かれるそうで、私は遺言書の中に書き加える事とした。
〈 菅笠・金剛杖・輪袈裟 〉

第1番 霊山寺横の売店で、金剛杖・白衣(おいづる)・輪袈裟・菅笠・納経帳を買い、身につけると、一見で お遍路 と分かる姿となった。 金剛杖について学んだ事を、ここに書き残しておく。
1.遍路とお遍路
遍路とは、弘法大師(お大師様)が開いた四国八十八ヶ所霊場(札所)を巡拝(巡礼)することで、
巡拝する人が お遍路 と呼ばれ、地元の人は敬意と親しみを込め、お遍路さんと呼ぶ。
2.同行二人(どうぎょうににん)
買った金剛杖と菅笠には、同行二人と書かれており、これは遍路には お大師様がついて一緒に
歩いてくれている事を示し、特に金剛杖はお大師様の分身・化身と教えられた。
この教えは、一人で遍路道を歩いて行く私にとって、心強く感じられた。
お遍路を泊める宿の多くでは、お遍路が宿に辿り着くと「お杖を、洗いましょう。」と受け取り、清水で
洗い手拭で拭いたあとで返してくれる。 その金剛杖を泊まり部屋の中に持ち込み、床の間か部屋の一番良い場所に立てかけるように、言われた。
お杖を洗うのは、金剛杖をお大師様そのものと考え、遍路旅で汚れたに違いないお大師様の足を
洗って差し上げるものだった。
3.死出の旅
江戸時代に盛んになってきた四国遍路では、現代とは比較にならない厳しい歩き旅をするもので、
四国遍路は死出の旅と言われていた。
お大師様の救いを願って遍路に出た、病苦や悩み等を抱えた人もいて、それらの人達の中には遍路途中で行き倒れることも多くあったそうだ。
お遍路さんが遍路途中に亡くなると、その土地の人が、亡くなったお遍路さんを土に埋め、その上に金剛杖を立てたもので、金剛杖は墓標の役割も果たしたと言われている。
4.墓標代わり
五輪塔とは、死者へ対する供養や墓標として造られた石塔で、その形は「5大」を表した5種類の
パ-ツから出来ている。
金剛杖の頭部には、この「5大」が梵字で刻まれており、この部分は大切なものとして、直接手に触れないように錦布で包まれている。
昔の四国遍路では、行き倒れ亡くなったお遍路の金剛杖を、墓標として使っていたそうだ。
5.私の金剛杖
四国あるき遍路を、乗り物を一切使わず 45泊46日の通し で結願出来たのは、金剛杖にいつも
支えられていた気持ちのお蔭と、実感している。
四国遍路を結願し、第88番 大窪寺に金剛杖を納める人たちも居るそうだが、私は記念に家に持ち帰った。
あるガイドブックによると、死出の際に四国遍路に使った金剛杖を棺桶に入れてもらう と、その人は
浄土へ導かれるそうで、私は遺言書の中に書き加える事とした。
〈 菅笠・金剛杖・輪袈裟 〉
花ごよみ 十一月
2024年11月25日
狭い庭を使い、季節を知らせる花が咲く草木をと心掛け、園芸の真似事をしてきました。
傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 十一月 は、 ツワブキ です。
我が家の ツワブキ は、釣りの帰りに野山に自生の株を少し持ち帰り、植えたものです。
庭の片隅でも丈夫に育ち、十一月頃に黄色い花を咲かせ、花は長持ちし甘い香りを放ってくれます
ので、私が好きな植物の一つです。
葉はフキと似た形ですが、葉は厚く常緑性で、キク科の植物だそうです。
そう言えば、黄色い花の形はキクに似ています。
十一月に、この花が咲き出すと、今年一年も終わりに近づいた事を、悟らされれます。
〈 ツワブキ の花 〉 〈 半日蔭でも育つ ツワブキ 〉


傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 十一月 は、 ツワブキ です。
我が家の ツワブキ は、釣りの帰りに野山に自生の株を少し持ち帰り、植えたものです。
庭の片隅でも丈夫に育ち、十一月頃に黄色い花を咲かせ、花は長持ちし甘い香りを放ってくれます
ので、私が好きな植物の一つです。
葉はフキと似た形ですが、葉は厚く常緑性で、キク科の植物だそうです。
そう言えば、黄色い花の形はキクに似ています。
十一月に、この花が咲き出すと、今年一年も終わりに近づいた事を、悟らされれます。
〈 ツワブキ の花 〉 〈 半日蔭でも育つ ツワブキ 〉
ボジョレヌ-ボ-なぜですか?
2024年11月19日
ア-カイブ記事 公開 : 2011年11月15日
その年のボジョレヌ-ボ-を飲める解禁日は、11月第3木曜日と決められているそうです。
日本では、いつも当日のニュ-スで大きく取り上げられますが、友人のW氏はこの騒ぎを、何事も
本質を知ろうとせず、踊らされ易い日本人の姿の一つだと、嘆きます。
24年前の11月10日に、最初の駐在国としてベルギ-に赴任し、ブリュッセルに住み始めました。
しばらく過ぎての街角歩きの時、ある店先で陽が当たる場所に、バケツの中にワインを立て売られており、その価格が非常に安いのに驚きました。
翌日、駐在先輩のW氏に話したところ、「それはボジョレヌ-ボ-だが、ブドウジュ-スを醗酵させたもので 未熟ワイン だ。 言い換えれば、ワインもどきさ。 あんな物を飲むものではないよ。」と、
言われました。
駐在が長い彼は、ワインを学び楽しみ、TPOで飲み分けるワイン通となっており、ボジョレヌ-ボ-について教えてくれました。

1.ワインの製造プロセス
①.8~9月頃、ブドウの実が摘まれる。
②.大タンクに入れられた実は押しつぶされ、実汁と皮が一緒になった状態で、
1次醗酵が始まる。
③.ある期間醗酵を続けたあとで、こされてカスが取り除かれ、第一段階のワイン元酒となる。
④.このワイン元酒は、樽に入れられ、翌年の春まで第2次醗酵しながら、寝かせられる。
⑤.第2次醗酵を経て、樽からボトル詰めにされ、出荷される。(これまでに最低6ヶ月かかる。)
⑥.ボトルワインは、10~15℃の管理温度の下、ボトルの中で第3次醗酵を続ける。
⑦.ワイン購入者は、自宅のワインセラ-で保管し、時と共にワインが育つのを楽しみながら飲む。
2.ボジョレヌ-ボ-
8月に摘んだブドウの実から作られ、ワイン元酒は2ヶ月足らずでボトル詰めの製品となり、日本には11月上旬には届いている。
第一段階のワイン元酒のボトル詰めは、言い換えればブドウジュ-ス醗酵酒 のワインもどき。
ワインを知る欧米の知識人 は、ボジョレヌ-ボ-を、一般ワインとしては飲まない。
3.他のフランスワイン産地 では?
ボルド-とブルゴ-ニュがフランスワインの二大産地だが、ボジョレ地区 が行う ワインもどきでの生産出荷は絶対しない。
ボジョレヌ-ボ-が正しいワイン製法で本物ワインと評価されるなら、他のフランスワイン産地も同じようにするはずだ。
短期間でワインとしての出荷なら、手間暇掛けずに早期の売り上げとなり、より儲かるものだ。
4.11月第3木曜日が解禁日?
説は、いくつかあるが、第二次大戦中にドイツ軍に占領され、ワインを徴収されたボジョレ-地区は、戦後になって飲むワインが無くなり、翌年春まで待つことが出来ず、新しく解禁日なるものを作り、
未熟ワインで平和を祝ったとも云われている。
今では、解禁日を設ける事で、消費者に価値のある物のように思わせる、巧みな商法と云える。
5.ボジョレヌ-ボ-の値段は妥当?
原価は、通常ボトルでせいぜい2~300円位 だ。 日本で飲むボジョレヌ-ボ-は、高い宣伝費+飛行機代+利益マ-ジンで、高くなっている。 つまりボジョレヌ-ボ-を飲む者は、価値ある
ワインに高いお金を払っているのではない。
安い原価のブド-ジュ-ス酒を、ボジョレの戦略と宣伝で、高値で売るボロ儲けの商売。 本質を
見抜けぬ人達がいる限り、このボロイ商売は続く。
友人のW氏は、11月第3木曜日の騒ぎのニュ-スを聞くと、「いつになっても、本質を知らずに踊ら
される輩が減らず、それら日本人は実に情けないことだ。」と嘆いてきます。
昨年、私は、「自分のお金で買って飲むのだから、良いんじゃないの。タデ喰う虫も好きずきと
思えば。」と言ってみました。
すると彼は、「タデを食う虫は、タデを分かって喰っているんだ。 ワインの勉強もせずに、マスコミが
取り上げるから踊らされて飲み、ワインと言えないものを美味しいワインだなどと言っていることに、我慢出来ない。 欧米の知識人に、日本人の本質を見抜けぬ低いレベルを晒しているものだ。」と、
さらに怒りを膨らませました。
今週末、W氏がまた憤慨の電話をしてくるのでは?と、思いつつ、焼酎のお湯割りを飲みながら、
この記事を書きました。
追記 : 2024年11月19日
今年のボジョレヌ-ボ-の解禁日は、11月21日です。
今年も、ロシア上空を飛べない航空機の運賃コストの大幅UPと、1ドル150円台となった円安などの為、さらに大幅な値上げとなるボジョレヌーボ-。
今年もマスコミに踊らされる人たちが、いるのでしょうか?
その年のボジョレヌ-ボ-を飲める解禁日は、11月第3木曜日と決められているそうです。
日本では、いつも当日のニュ-スで大きく取り上げられますが、友人のW氏はこの騒ぎを、何事も
本質を知ろうとせず、踊らされ易い日本人の姿の一つだと、嘆きます。
24年前の11月10日に、最初の駐在国としてベルギ-に赴任し、ブリュッセルに住み始めました。
しばらく過ぎての街角歩きの時、ある店先で陽が当たる場所に、バケツの中にワインを立て売られており、その価格が非常に安いのに驚きました。
翌日、駐在先輩のW氏に話したところ、「それはボジョレヌ-ボ-だが、ブドウジュ-スを醗酵させたもので 未熟ワイン だ。 言い換えれば、ワインもどきさ。 あんな物を飲むものではないよ。」と、
言われました。
駐在が長い彼は、ワインを学び楽しみ、TPOで飲み分けるワイン通となっており、ボジョレヌ-ボ-について教えてくれました。
1.ワインの製造プロセス
①.8~9月頃、ブドウの実が摘まれる。
②.大タンクに入れられた実は押しつぶされ、実汁と皮が一緒になった状態で、
1次醗酵が始まる。
③.ある期間醗酵を続けたあとで、こされてカスが取り除かれ、第一段階のワイン元酒となる。
④.このワイン元酒は、樽に入れられ、翌年の春まで第2次醗酵しながら、寝かせられる。
⑤.第2次醗酵を経て、樽からボトル詰めにされ、出荷される。(これまでに最低6ヶ月かかる。)
⑥.ボトルワインは、10~15℃の管理温度の下、ボトルの中で第3次醗酵を続ける。
⑦.ワイン購入者は、自宅のワインセラ-で保管し、時と共にワインが育つのを楽しみながら飲む。
2.ボジョレヌ-ボ-
8月に摘んだブドウの実から作られ、ワイン元酒は2ヶ月足らずでボトル詰めの製品となり、日本には11月上旬には届いている。
第一段階のワイン元酒のボトル詰めは、言い換えればブドウジュ-ス醗酵酒 のワインもどき。
ワインを知る欧米の知識人 は、ボジョレヌ-ボ-を、一般ワインとしては飲まない。
3.他のフランスワイン産地 では?
ボルド-とブルゴ-ニュがフランスワインの二大産地だが、ボジョレ地区 が行う ワインもどきでの生産出荷は絶対しない。
ボジョレヌ-ボ-が正しいワイン製法で本物ワインと評価されるなら、他のフランスワイン産地も同じようにするはずだ。
短期間でワインとしての出荷なら、手間暇掛けずに早期の売り上げとなり、より儲かるものだ。
4.11月第3木曜日が解禁日?
説は、いくつかあるが、第二次大戦中にドイツ軍に占領され、ワインを徴収されたボジョレ-地区は、戦後になって飲むワインが無くなり、翌年春まで待つことが出来ず、新しく解禁日なるものを作り、
未熟ワインで平和を祝ったとも云われている。
今では、解禁日を設ける事で、消費者に価値のある物のように思わせる、巧みな商法と云える。
5.ボジョレヌ-ボ-の値段は妥当?
原価は、通常ボトルでせいぜい2~300円位 だ。 日本で飲むボジョレヌ-ボ-は、高い宣伝費+飛行機代+利益マ-ジンで、高くなっている。 つまりボジョレヌ-ボ-を飲む者は、価値ある
ワインに高いお金を払っているのではない。
安い原価のブド-ジュ-ス酒を、ボジョレの戦略と宣伝で、高値で売るボロ儲けの商売。 本質を
見抜けぬ人達がいる限り、このボロイ商売は続く。
友人のW氏は、11月第3木曜日の騒ぎのニュ-スを聞くと、「いつになっても、本質を知らずに踊ら
される輩が減らず、それら日本人は実に情けないことだ。」と嘆いてきます。
昨年、私は、「自分のお金で買って飲むのだから、良いんじゃないの。タデ喰う虫も好きずきと
思えば。」と言ってみました。
すると彼は、「タデを食う虫は、タデを分かって喰っているんだ。 ワインの勉強もせずに、マスコミが
取り上げるから踊らされて飲み、ワインと言えないものを美味しいワインだなどと言っていることに、我慢出来ない。 欧米の知識人に、日本人の本質を見抜けぬ低いレベルを晒しているものだ。」と、
さらに怒りを膨らませました。
今週末、W氏がまた憤慨の電話をしてくるのでは?と、思いつつ、焼酎のお湯割りを飲みながら、
この記事を書きました。
追記 : 2024年11月19日
今年のボジョレヌ-ボ-の解禁日は、11月21日です。
今年も、ロシア上空を飛べない航空機の運賃コストの大幅UPと、1ドル150円台となった円安などの為、さらに大幅な値上げとなるボジョレヌーボ-。
今年もマスコミに踊らされる人たちが、いるのでしょうか?
歩き遍路 準備・持ち物
2024年11月15日
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月5日
7月より、四国あるき遍路へのトレ-ニングとして、奥多摩・高水三山コ-スの山歩きを6回行い、
山道も多い遍路道歩きに適した持ち物を考え、必要となる品々を、揃えていった。
高水三山は軽登山コ-スだが、急坂や歩きづらい箇所が結構あって、背負うリュックの不具合や、
悪路を歩く際の靴の大事さが分かり、それらの購入時に、反映させた。
A..装備品
1.荷物入れ … deuter 社 リュック 22 L 雨よけカバ-付、ウエストポ-チ、エコバッグ
2.雨具類 … 大きい折り畳み傘(カ-ボンファイバ- 製)、ゴアテックス上雨着、雨ズボン、防寒シ-ト
3.記録具類 … デジタルカメラ、ICレコ-ダ-、日誌用ノ-ト、筆記具、スマホ、
4.地図類 … 巡礼ル-ト地図コピ-、5万分の1地図要所9枚、拡大鏡、コンパス
5.薬類 … バンドエイド、オロナイン、タイアシンA(靴ずれ・すり傷)、ムヒアルファEX、水虫薬
6.洗面具類 … 歯ブラシ、歯磨きクリ-ム、シェ-バ-、爪切、ドライヤ-(濡れ物 乾し用)
7.お詣り用品 … お数珠、ロ-ソク、線香、風防ライタ-
8.その他 … 郵貯カ-ド、充電器3個(スマホ、デジカメ、電池)、果物ナイフ、LED懐中電灯、
耳栓、アイマスク、汗止めバンド、タオル2枚、非常用食糧、健康保険証
*当初のリストアップより、かなり削ったが、最終的に12Kg の荷物 になっていた。
B.服装
・10月初旬の服装+ブルゾンとした。 着替え下着1組、腹巻、5本指ソックス3組。
・靴 … ミズノ トレッキングシュ-ズ (ゴアテックス、1センチ大き目サイズ)
・帽子 … AIGLE 社 レインハット
*初めて歩き遍路を行った人の多くが、足のマメで苦しみ、中にはそれが原因で挫折の人もいたが、私は最適の靴+5本指ソックスの組み合わせ効果により、一度もマメは出来ず、歩き通せた。
なお、持ち物への評価は、別途行う予定。
C.お遍路用品
第1番 霊山寺で、金剛杖・白衣(オイズル)・輪袈裟・菅笠・納経帳を購入し、お遍路姿になった。
〈 あるき遍路 装備・姿恰好の一例 〉
追記 : 2013年12月5日
四国一周の1400Kmを歩き通せたのは、特に歩きに適したトレッキングシュ-ズと、長時間
背負っても疲れないリュックの選択が良かった
と言える。
経験から加えたいのは、必携バイブル地図と、
トンネル歩き時に3Dマスクだ。
歩き遍路のバイブル
2024年11月12日
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月18日
四国あるき遍路に向けて、まず札所の所在地・札所間の距離・難所・宿などの情報を集めた。
次に、右回り順の88ヶ寺+10ヶ寺のリストを作り、集めた情報を全て入れ、一覧表とした。
この一覧表から、毎日どこまで札所をお詣り出来、どこ辺りで泊まるかを計り、おおよその日程を
書き込み、全体日程を把握し予算を組んだ。
地図の準備は、ガイド本の札所ル-トのイラストをコピ-し、詳しい地図情報が欲しい土地・地域は
5万分の1地図を買った。
インタ-ネットの 四国八十八ヶ所お遍路地図 を開き、参考になる地図を、プリントアウトした。
宿情報は、ガイド本巻末にある宿リストをコピ-し、ネット 四国八十八ヶ所巡礼の宿泊所の一覧 の宿情報もプリントアウトした。 出発前には、5泊目までの宿予約を入れておいた。
これらの準備で、10月4日より四国あるき遍路をスタ-トし、第12番の焼山寺までは道に迷うことなく進めた。 しかし、その後は札所ル-トのイラスト図には載らない実際の道が沢山あり(当たり前の事。)、道の分岐点でどちらに進むべきか迷い、何度も無駄歩きを重ね、宿の所在地がよく分から
なかったり等、苦戦の連続となった。
7泊目となった民宿「鮒の里」は、歩く道に広告板を見つけ、その日の宿泊予約をしたが、歩く道沿いにあった宿を見落とし先に進んでしまい、その宿に辿り着いた時は、他の遍路客は食事を終えよう
とした時間だった。
遅れて食堂に入った私に、先着の遍路客から遅い理由を尋ねられた。 私が出発前に用意し使い
始めた地図類・資料を見せたら、「これでは、歩き遍路は出来ないよ。」と、言われてしまった。
全員が持っていた地図本は、へんろみち保存協力会発行の「四国遍路ひとり歩き同行二人」で、
「この先あるき遍路を続けるなら、早く入手して使うように。」と、アドバイスを受けた。
一人は、「宮崎建樹さんが作られたこの地図本は、歩き遍路に必要な情報が全て織り込まれている。 この地図本なくして、歩き遍路は出来ないよ。 歩き遍路者へのバイブル と言われている。」と、話してくれた。

彼らは四国に入る前に、この地図本を入手しており、通信販売で取寄せたか、
東京なら八重洲ブックセンタ-で買っていたそうだ。
四国に入ってしまった遍路者は、特定の札所売店で購入する手段があると
教わり、各札所の売店で探したが、入手出来たのは、その日から26日も過ぎた、第54番 延命寺 の売店だった。
バイブルと言われた地図本を開くと、出発前に時間を掛けて集めた情報が全て含まれており、また
使い勝手が良く、その後の歩き遍路は、比較にならないほど楽なものとなった。
準備に使った時間やコピ-は無駄だった事と、地図情報の不足より起きた苦労は、今回の歩き旅の3分の2の日程で起きていたものだった。
なお、仏教のお寺を巡礼する四国あるき遍路の地図本に、バイブルと云う言葉が使えるか?と、辞書で調べてみると、 【 バイブル…②.それぞれの分野で、権威のある書物。】 とあり、納得できた。
四国あるき遍路に向けて、まず札所の所在地・札所間の距離・難所・宿などの情報を集めた。
次に、右回り順の88ヶ寺+10ヶ寺のリストを作り、集めた情報を全て入れ、一覧表とした。
この一覧表から、毎日どこまで札所をお詣り出来、どこ辺りで泊まるかを計り、おおよその日程を
書き込み、全体日程を把握し予算を組んだ。
地図の準備は、ガイド本の札所ル-トのイラストをコピ-し、詳しい地図情報が欲しい土地・地域は
5万分の1地図を買った。
インタ-ネットの 四国八十八ヶ所お遍路地図 を開き、参考になる地図を、プリントアウトした。
宿情報は、ガイド本巻末にある宿リストをコピ-し、ネット 四国八十八ヶ所巡礼の宿泊所の一覧 の宿情報もプリントアウトした。 出発前には、5泊目までの宿予約を入れておいた。
これらの準備で、10月4日より四国あるき遍路をスタ-トし、第12番の焼山寺までは道に迷うことなく進めた。 しかし、その後は札所ル-トのイラスト図には載らない実際の道が沢山あり(当たり前の事。)、道の分岐点でどちらに進むべきか迷い、何度も無駄歩きを重ね、宿の所在地がよく分から
なかったり等、苦戦の連続となった。
7泊目となった民宿「鮒の里」は、歩く道に広告板を見つけ、その日の宿泊予約をしたが、歩く道沿いにあった宿を見落とし先に進んでしまい、その宿に辿り着いた時は、他の遍路客は食事を終えよう
とした時間だった。
遅れて食堂に入った私に、先着の遍路客から遅い理由を尋ねられた。 私が出発前に用意し使い
始めた地図類・資料を見せたら、「これでは、歩き遍路は出来ないよ。」と、言われてしまった。
全員が持っていた地図本は、へんろみち保存協力会発行の「四国遍路ひとり歩き同行二人」で、
「この先あるき遍路を続けるなら、早く入手して使うように。」と、アドバイスを受けた。
一人は、「宮崎建樹さんが作られたこの地図本は、歩き遍路に必要な情報が全て織り込まれている。 この地図本なくして、歩き遍路は出来ないよ。 歩き遍路者へのバイブル と言われている。」と、話してくれた。

彼らは四国に入る前に、この地図本を入手しており、通信販売で取寄せたか、
東京なら八重洲ブックセンタ-で買っていたそうだ。
四国に入ってしまった遍路者は、特定の札所売店で購入する手段があると
教わり、各札所の売店で探したが、入手出来たのは、その日から26日も過ぎた、第54番 延命寺 の売店だった。
バイブルと言われた地図本を開くと、出発前に時間を掛けて集めた情報が全て含まれており、また
使い勝手が良く、その後の歩き遍路は、比較にならないほど楽なものとなった。
準備に使った時間やコピ-は無駄だった事と、地図情報の不足より起きた苦労は、今回の歩き旅の3分の2の日程で起きていたものだった。
なお、仏教のお寺を巡礼する四国あるき遍路の地図本に、バイブルと云う言葉が使えるか?と、辞書で調べてみると、 【 バイブル…②.それぞれの分野で、権威のある書物。】 とあり、納得できた。
なぜ四国遍路に?
2024年11月09日
ア-カイブ記事 公開 : 2012年11月24日
四国遍路の旅では、宿の夕食が6時からで、札所巡りを行っている人たちは、一緒の食事となった。
一日の札所巡りを終え、風呂でさっぱりした後の食事時間に、お互いの出身地・札所巡り期間・体験などを語り合い、また情報交換など出来、楽しく貴重な時間だった。
既に何周も四国あるき遍路行っている人達もいて、それらの人のアドバイスや情報などは、初めて歩き遍路を行う私にとって、大いに役立った。
また、この夕食の会話の中で、歩き遍路の経験者は、初めて行っている私に、「四国あるき遍路を、何故行うのか?」との質問を、よくしてきた。
私はいつも、「定年退職した私は、家に居てもする事はなく、家では山の神に支配されて面白くなく、この状況から抜け出るには長い旅が良いと考えた。 四国の札所巡礼に行くと言えば解ってもらえ、実行に移せた。」と、答えていた。
しかし、実際は老両親の介護を終えた後、心の中に死への戸惑い・慄き が強く心を占め、しばらく
悩んだ後に 般若心経 を知り、「空」の理念も理解出来ると、悩みから解き放たれていた。
さらに、四国遍路では札所にお詣りする時に、般若心経を唱えると知り、覚えたお経を札所で唱えてみようと、四国遍路を考えるようになっていった。
般若心経の関連書物から、昔の人々は四国遍路は 死出の旅 の覚悟で出掛けた事を知り、
私も昔の人々と同じ方法の通しで歩いて行う あるき遍路を行い、何かしら心に得てみたいと考え、
四国遍路に出たものだった。
〈 60番 横峰寺への登り遍路道 〉

追記 : 2024年11月9日
平成24年10月3日~11月17日に、歩きのみでの四国遍路を行い、結願して得たものは、沢山の
楽しく良い思い出だった。 ブログ記事をアーカイブで読み返し、四国遍路の思い出を楽しんでいる。
四国遍路の旅では、宿の夕食が6時からで、札所巡りを行っている人たちは、一緒の食事となった。
一日の札所巡りを終え、風呂でさっぱりした後の食事時間に、お互いの出身地・札所巡り期間・体験などを語り合い、また情報交換など出来、楽しく貴重な時間だった。
既に何周も四国あるき遍路行っている人達もいて、それらの人のアドバイスや情報などは、初めて歩き遍路を行う私にとって、大いに役立った。
また、この夕食の会話の中で、歩き遍路の経験者は、初めて行っている私に、「四国あるき遍路を、何故行うのか?」との質問を、よくしてきた。
私はいつも、「定年退職した私は、家に居てもする事はなく、家では山の神に支配されて面白くなく、この状況から抜け出るには長い旅が良いと考えた。 四国の札所巡礼に行くと言えば解ってもらえ、実行に移せた。」と、答えていた。
しかし、実際は老両親の介護を終えた後、心の中に死への戸惑い・慄き が強く心を占め、しばらく
悩んだ後に 般若心経 を知り、「空」の理念も理解出来ると、悩みから解き放たれていた。
さらに、四国遍路では札所にお詣りする時に、般若心経を唱えると知り、覚えたお経を札所で唱えてみようと、四国遍路を考えるようになっていった。
般若心経の関連書物から、昔の人々は四国遍路は 死出の旅 の覚悟で出掛けた事を知り、
私も昔の人々と同じ方法の通しで歩いて行う あるき遍路を行い、何かしら心に得てみたいと考え、
四国遍路に出たものだった。
〈 60番 横峰寺への登り遍路道 〉
追記 : 2024年11月9日
平成24年10月3日~11月17日に、歩きのみでの四国遍路を行い、結願して得たものは、沢山の
楽しく良い思い出だった。 ブログ記事をアーカイブで読み返し、四国遍路の思い出を楽しんでいる。
入間基地 航空祭
2024年11月02日
ア-カイブ記事 公開 : 2011年11月7日
毎年11月3日に行われます、航空自衛隊入間基地の、入間航空祭に行って来ました。
昨年8月に、横田基地の友好祭に、英会話講師から誘われ訪れており、比べて見学したい気持ちがありました。
西武線所沢駅で飯能行きの電車に乗り替えると、乗り切れないほどの混み様でしたが、通勤電車
との違いは、車内で楽しい話し声があちこちでしていることでした。
自衛隊基地は稲荷山公園駅に隣接ですが、人・人・人・人…で臨時改札を通り手荷物検査を受け、
基地内での自由行動地点までに約50分もかかりました。
 飛行場地区には、たくさんの航空機が展示されており、大型輸送機などは機内を見物出来、
飛行場地区には、たくさんの航空機が展示されており、大型輸送機などは機内を見物出来、
長い行列が出来ていました。
上空では、大型機の編隊飛行や空挺部隊の
パラシュ-ト降下などのデモ飛行が、次々と
続きました。
アトラクション会場では、中部航空音楽隊のブラスバンド演奏があり、耳を楽しませてくれました。
この会場の壁には、東日本大震災の災害派遣で活躍された、入間基地の隊員の活動内容が写真展示されており、困難な状況下において、様々な支援実績をあげられたことが、分かりました。
また、全国から集まった救援物資を、空輸するためのタ-ミナルが、入間基地でした。
厳しい環境下で勤務された自衛隊の皆様、ご苦労様でした。 感謝、感謝です。
広い基地内に決められた場所には、レジャ-シ-トを拡げ、持参の飲食物を楽しみながら、上空の
デモ飛行を楽しむ家族連れがたくさんいました。
今年の入場者は、17万人だったそうですが、入場無料で盛り沢山の行事を楽しめる事から、毎年
訪れる家族連れが多いそうです。
横田基地の友好祭と比べると、入間航空祭のほうが中身がずっと濃く、より楽しめる内容でした。
航空祭の目玉イベントは、ブル-インパルスの飛行ショ-で、これは横田基地友好祭では見られ
ないものです。
敷地内には売店エリアがあり、食べ物の他に自衛隊グッズなどの販売もあり、私は土産として
よこすか海軍カレ-を買い、夕飯に美味しく食べました。
追記 : 2022年11月1日
コロナ禍で中止となっていました入間基地 航空祭は、今年は開催されます。
航空自衛隊 入間基地 公式サイト http://www.mod.go.jp/asdf/iruma/
毎年11月3日に行われます、航空自衛隊入間基地の、入間航空祭に行って来ました。
昨年8月に、横田基地の友好祭に、英会話講師から誘われ訪れており、比べて見学したい気持ちがありました。
西武線所沢駅で飯能行きの電車に乗り替えると、乗り切れないほどの混み様でしたが、通勤電車
との違いは、車内で楽しい話し声があちこちでしていることでした。
自衛隊基地は稲荷山公園駅に隣接ですが、人・人・人・人…で臨時改札を通り手荷物検査を受け、
基地内での自由行動地点までに約50分もかかりました。
 飛行場地区には、たくさんの航空機が展示されており、大型輸送機などは機内を見物出来、
飛行場地区には、たくさんの航空機が展示されており、大型輸送機などは機内を見物出来、長い行列が出来ていました。
上空では、大型機の編隊飛行や空挺部隊の
パラシュ-ト降下などのデモ飛行が、次々と
続きました。
アトラクション会場では、中部航空音楽隊のブラスバンド演奏があり、耳を楽しませてくれました。
この会場の壁には、東日本大震災の災害派遣で活躍された、入間基地の隊員の活動内容が写真展示されており、困難な状況下において、様々な支援実績をあげられたことが、分かりました。
また、全国から集まった救援物資を、空輸するためのタ-ミナルが、入間基地でした。
厳しい環境下で勤務された自衛隊の皆様、ご苦労様でした。 感謝、感謝です。
広い基地内に決められた場所には、レジャ-シ-トを拡げ、持参の飲食物を楽しみながら、上空の
デモ飛行を楽しむ家族連れがたくさんいました。
今年の入場者は、17万人だったそうですが、入場無料で盛り沢山の行事を楽しめる事から、毎年
訪れる家族連れが多いそうです。
横田基地の友好祭と比べると、入間航空祭のほうが中身がずっと濃く、より楽しめる内容でした。
航空祭の目玉イベントは、ブル-インパルスの飛行ショ-で、これは横田基地友好祭では見られ
ないものです。
敷地内には売店エリアがあり、食べ物の他に自衛隊グッズなどの販売もあり、私は土産として
よこすか海軍カレ-を買い、夕飯に美味しく食べました。
追記 : 2022年11月1日
コロナ禍で中止となっていました入間基地 航空祭は、今年は開催されます。
航空自衛隊 入間基地 公式サイト http://www.mod.go.jp/asdf/iruma/
四国遍路 記念日
2024年10月03日
もう12年前となる 2012年10月4日、四国遍路の旅に出掛けています。
鳴門から歩き出し、乗り物を一切使わず に、46日間 を掛け四国一周の遍路旅を結願出来ました。
八十八ヶ寺の結願の後は、第10番寺に進み更に第1番寺まで戻り、数珠の形旅を完成しています。
最終日には、高野山を訪れ無事の四国遍路のお礼参りも出来ています。
あの年の四国の10月は、ほとんどが好天の日で、連日 大汗をかきながら歩いたものでした。
この旅での体験を、ボブのブログ「四国あるき遍路」で記事公開しており、時々読み返し懐かしく
思い出しています。
四国を、通し(10 4)で歩いた思い出の日として、10月4日を 四国遍路 記念日 と決めました。
我がブログ記事 「お遍路の一日」 を開き、楽しかった お遍路旅 を思い出してみます。
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月22日
四国あるき遍路の一日は、おおよそ次のように流れた。
〈 前夜、お遍路民宿に泊まる。 〉
5時30分 起床 ・洗顔 ・体操+ストレッチ ・TV 天気予報当日の確認
6時00分 朝食 ・他の遍路者と一緒の食事。 ・茶碗飯大盛り2杯、おかずも残さず食べる。
・朝食後に、宿代・前夜飲み物代の支払い。
・共同トイレの空きをみて、朝の大トイレ。(とても重要。体を軽く。)
・部屋に戻り、身支度。 ・その日の歩きコ-ス確認。
7時00分 宿立ち ・札所目指して、遍路歩きスタ-ト。
・ひたすら歩き、約90分毎に、10分位の休憩。(長く休むのは N.G. )
・休憩時に、水分補給。 ・菓子/果物などでカロリ-補給
・札所では、本堂と大師堂それぞれにお詣り。( 般若心経の読経。ご朱印受け。)
*一つの札所お詣りに、約30分は掛かる。
*ひたすら歩くだけの日と、1日に何ヶ所もの札所巡りの日がある。
12時頃 昼食 ・食事が出来る店が無い場合が多い。 ・途中で買った弁当を食べる。
・弁当を買えない場合は、リュックに用意の非常食/菓子などを食べる。
・昼食後、再び歩く。 ・天気の日は大汗をかき、水分の補給を頻繁に行う。
・10月中は、ペットボトル大を、毎日5~6本飲んだ。
15時頃 宿予約 ・残り2時間で行き着ける辺りの宿に、スマホで宿泊予約。
・ひたすら歩き続け、宿に向かう。
17時頃 宿入り ・宿帳に記入。 ・入浴。(入浴中に足のマッサ-ジ。)
・大汗をかき濡れた衣類のコイン洗濯。(ほぼ毎日)
18時00分夕食 ・他の遍路者と一緒の食事。 ・まずはビ-ル大瓶1本。
・食事時間に、情報交換。 ・歓談。一番楽しい時間。
19時頃 部屋に ・洗濯物のコイン乾燥。 ・日誌つけ。 ・翌日ル-ト/歩行予定距離確認。
・スマホ他の充電 ・リュック中身の確認と整理。 ・TV天気予報を見る。
21時 就寝 ・寝具敷き ・耳栓/アイマスク ・懐中電灯枕元に。
*ビジネスホテルは夕食なく、外に出て食事。 朝食が出ても7時から。
*1日に歩く距離は、その日訪れる札所の数如何と、山道/平地で異なる。
山道多い日は、20~30Km。 平地を歩く日は、40Km。 最長歩いた日は、50Km。
歩き進むと、日々変わる景色・農作物の変化・四国各地の人の暮らし等を見て学べ、お接待など
多くの方のお世話になりながら、毎日が新鮮で楽しい思い出が残っていった。
鳴門から歩き出し、乗り物を一切使わず に、46日間 を掛け四国一周の遍路旅を結願出来ました。
八十八ヶ寺の結願の後は、第10番寺に進み更に第1番寺まで戻り、数珠の形旅を完成しています。
最終日には、高野山を訪れ無事の四国遍路のお礼参りも出来ています。
あの年の四国の10月は、ほとんどが好天の日で、連日 大汗をかきながら歩いたものでした。
この旅での体験を、ボブのブログ「四国あるき遍路」で記事公開しており、時々読み返し懐かしく
思い出しています。
四国を、通し(10 4)で歩いた思い出の日として、10月4日を 四国遍路 記念日 と決めました。
我がブログ記事 「お遍路の一日」 を開き、楽しかった お遍路旅 を思い出してみます。
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月22日
四国あるき遍路の一日は、おおよそ次のように流れた。
〈 前夜、お遍路民宿に泊まる。 〉
5時30分 起床 ・洗顔 ・体操+ストレッチ ・TV 天気予報当日の確認
6時00分 朝食 ・他の遍路者と一緒の食事。 ・茶碗飯大盛り2杯、おかずも残さず食べる。
・朝食後に、宿代・前夜飲み物代の支払い。
・共同トイレの空きをみて、朝の大トイレ。(とても重要。体を軽く。)
・部屋に戻り、身支度。 ・その日の歩きコ-ス確認。
7時00分 宿立ち ・札所目指して、遍路歩きスタ-ト。
・ひたすら歩き、約90分毎に、10分位の休憩。(長く休むのは N.G. )
・休憩時に、水分補給。 ・菓子/果物などでカロリ-補給
・札所では、本堂と大師堂それぞれにお詣り。( 般若心経の読経。ご朱印受け。)
*一つの札所お詣りに、約30分は掛かる。
*ひたすら歩くだけの日と、1日に何ヶ所もの札所巡りの日がある。
12時頃 昼食 ・食事が出来る店が無い場合が多い。 ・途中で買った弁当を食べる。
・弁当を買えない場合は、リュックに用意の非常食/菓子などを食べる。
・昼食後、再び歩く。 ・天気の日は大汗をかき、水分の補給を頻繁に行う。
・10月中は、ペットボトル大を、毎日5~6本飲んだ。
15時頃 宿予約 ・残り2時間で行き着ける辺りの宿に、スマホで宿泊予約。
・ひたすら歩き続け、宿に向かう。
17時頃 宿入り ・宿帳に記入。 ・入浴。(入浴中に足のマッサ-ジ。)
・大汗をかき濡れた衣類のコイン洗濯。(ほぼ毎日)

18時00分夕食 ・他の遍路者と一緒の食事。 ・まずはビ-ル大瓶1本。
・食事時間に、情報交換。 ・歓談。一番楽しい時間。
19時頃 部屋に ・洗濯物のコイン乾燥。 ・日誌つけ。 ・翌日ル-ト/歩行予定距離確認。
・スマホ他の充電 ・リュック中身の確認と整理。 ・TV天気予報を見る。
21時 就寝 ・寝具敷き ・耳栓/アイマスク ・懐中電灯枕元に。
*ビジネスホテルは夕食なく、外に出て食事。 朝食が出ても7時から。
*1日に歩く距離は、その日訪れる札所の数如何と、山道/平地で異なる。
山道多い日は、20~30Km。 平地を歩く日は、40Km。 最長歩いた日は、50Km。
歩き進むと、日々変わる景色・農作物の変化・四国各地の人の暮らし等を見て学べ、お接待など
多くの方のお世話になりながら、毎日が新鮮で楽しい思い出が残っていった。
花ごよみ 九月 1 シュウカイドウ
2024年09月24日
狭い庭を使い、季節を知らせる花が咲く草木をと心掛け、園芸の真似事をしてきました。
傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 九月 1 は、 シュウカイドウ です。
シュウカイドウ(秋海棠)は、江戸時代に中国から園芸用に持ち込まれた帰化植物だそうです。
だいぶ前に、釣り場の帰り道の崖一面に、ピンクの花が咲く光景に目を奪われました。
何の植物か知りませんでしたので、数株持ち帰り調べて シュウカイドウ と分かりました。
日陰で育つとあり、北側の空いた地面に植えたものが、連綿と生き延びて秋になると、可憐な花を
咲かせます。
何の手入れも要らず、こぼれ種から毎年生えてきて、秋になると花で季節を知らせる 秋海棠 です。
〈 可憐な花のシュウカイドウ 〉 〈 日陰で元気なシュウカイドウ 〉


傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 九月 1 は、 シュウカイドウ です。
シュウカイドウ(秋海棠)は、江戸時代に中国から園芸用に持ち込まれた帰化植物だそうです。
だいぶ前に、釣り場の帰り道の崖一面に、ピンクの花が咲く光景に目を奪われました。
何の植物か知りませんでしたので、数株持ち帰り調べて シュウカイドウ と分かりました。
日陰で育つとあり、北側の空いた地面に植えたものが、連綿と生き延びて秋になると、可憐な花を
咲かせます。
何の手入れも要らず、こぼれ種から毎年生えてきて、秋になると花で季節を知らせる 秋海棠 です。
〈 可憐な花のシュウカイドウ 〉 〈 日陰で元気なシュウカイドウ 〉
Posted by ボブ at
23:02
│Comments(0)