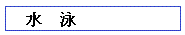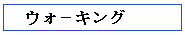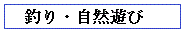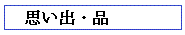2024年12月26日
花ごよみ 十二月
狭い庭を使い、季節を知らせる花が咲く草木をと心掛け、園芸の真似事をしてきました。
傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 十二月 は、 サザンカ です。
13年前に、終の棲家への家の建て替えを行いました。
元の家の取り壊しの際に、それまで狭い庭に植えてあった草木のすべても取り除かれました。
終の棲家が完成し、老い行く身に安心な住まいとなりましたが、何も植わって無い狭い庭は寂しく
ごろ石の混じった庭土の土振るいを行いながら、園芸プランを練りました。
建て替えの記念となり、花の少ない季節に咲く樹木は?と考え選んだのが サザンカ でした。
ホ-ムセンタ-で買い求め植えたサザンカは、毎年10月から咲き始め3ヶ月の間 次から次に花が咲き続いており、満足な選択でした。
〈 サザンカ 祖父江 〉 〈 木の高さは 1.5m 〉


傘寿を超え、やがて何も行えなくなりますが、ブログにアルバムのように記録しておけば、行ってきた細やかな園芸を、いつでも思い出すことが出来そうです。
花ごよみ 十二月 は、 サザンカ です。
13年前に、終の棲家への家の建て替えを行いました。
元の家の取り壊しの際に、それまで狭い庭に植えてあった草木のすべても取り除かれました。
終の棲家が完成し、老い行く身に安心な住まいとなりましたが、何も植わって無い狭い庭は寂しく
ごろ石の混じった庭土の土振るいを行いながら、園芸プランを練りました。
建て替えの記念となり、花の少ない季節に咲く樹木は?と考え選んだのが サザンカ でした。
ホ-ムセンタ-で買い求め植えたサザンカは、毎年10月から咲き始め3ヶ月の間 次から次に花が咲き続いており、満足な選択でした。
〈 サザンカ 祖父江 〉 〈 木の高さは 1.5m 〉
2024年12月13日
般若心経 歩き遍路回想
ア-カイブ記事 公開 : 2012年11月28日
初めて般若心経を聞いたのは、12年前に父が永眠し、遺骨がまだ家にある間に、親友のK氏が
訪れてくれ、焼香と読経をしてくれた時だった。
彼が般若心経をそらんじていた事に、少し驚いたが、心を込めて唱えられる般若心経を、有り難く
思いながら聴いた。 私も、般若心経を唱えられる様になりたいと思い、さっそく経文を入手し暗記を始め、覚える事が出来た。
般若心経を覚えた頃、NHK TV ドキュメント 柳沢桂子 般若心経について語る が放映された。
この番組を観て、柳沢桂子の生命科学者としての経歴、彼女を襲う難病との壮絶な闘い、その中で彼女が般若心経を翻訳し、『生きて死ぬ智慧』 として出版したことを知った。
さっそく、この本を買って読み、さらに般若心経を解釈する何冊かの他者の著書を読み、「空」の
理念が理解出来てくると、それまで抱いていた 死への戸惑い ・ 慄き が、心の中から消えていた。
それらの本の中で、四国札所巡礼のおりに、巡礼者は必ず般若心経を読経する習わしと知り、四国八十八ヶ所霊場巡礼に関心を持つようになった。
2010年4月~6月に、NHK ラジオ第2放送で「四国遍路を考える」(講師:真鍋俊照-- 四国霊場
第4番 大日寺住職・四国大学教授)が、13回にわたり放送され、欠かさず聞くことが出来た。
この講座から、四国遍路の歴史と世界を学び、元気な内に 四国あるき遍路を行ってみたい と
考え、実行したものだった。
〈 衛門三郎 と 弘法大師 〉
初めて般若心経を聞いたのは、12年前に父が永眠し、遺骨がまだ家にある間に、親友のK氏が
訪れてくれ、焼香と読経をしてくれた時だった。
彼が般若心経をそらんじていた事に、少し驚いたが、心を込めて唱えられる般若心経を、有り難く
思いながら聴いた。 私も、般若心経を唱えられる様になりたいと思い、さっそく経文を入手し暗記を始め、覚える事が出来た。
般若心経を覚えた頃、NHK TV ドキュメント 柳沢桂子 般若心経について語る が放映された。
この番組を観て、柳沢桂子の生命科学者としての経歴、彼女を襲う難病との壮絶な闘い、その中で彼女が般若心経を翻訳し、『生きて死ぬ智慧』 として出版したことを知った。
さっそく、この本を買って読み、さらに般若心経を解釈する何冊かの他者の著書を読み、「空」の
理念が理解出来てくると、それまで抱いていた 死への戸惑い ・ 慄き が、心の中から消えていた。
それらの本の中で、四国札所巡礼のおりに、巡礼者は必ず般若心経を読経する習わしと知り、四国八十八ヶ所霊場巡礼に関心を持つようになった。
2010年4月~6月に、NHK ラジオ第2放送で「四国遍路を考える」(講師:真鍋俊照-- 四国霊場
第4番 大日寺住職・四国大学教授)が、13回にわたり放送され、欠かさず聞くことが出来た。
この講座から、四国遍路の歴史と世界を学び、元気な内に 四国あるき遍路を行ってみたい と
考え、実行したものだった。
〈 衛門三郎 と 弘法大師 〉
2024年12月02日
金剛杖 歩き遍路回想
ア-カイブ記事 公開 : 2012年12月10日
第1番 霊山寺横の売店で、金剛杖・白衣(おいづる)・輪袈裟・菅笠・納経帳を買い、身につけると、一見で お遍路 と分かる姿となった。 金剛杖について学んだ事を、ここに書き残しておく。
1.遍路とお遍路
遍路とは、弘法大師(お大師様)が開いた四国八十八ヶ所霊場(札所)を巡拝(巡礼)することで、
巡拝する人が お遍路 と呼ばれ、地元の人は敬意と親しみを込め、お遍路さんと呼ぶ。
2.同行二人(どうぎょうににん)
買った金剛杖と菅笠には、同行二人と書かれており、これは遍路には お大師様がついて一緒に
歩いてくれている事を示し、特に金剛杖はお大師様の分身・化身と教えられた。
この教えは、一人で遍路道を歩いて行く私にとって、心強く感じられた。
お遍路を泊める宿の多くでは、お遍路が宿に辿り着くと「お杖を、洗いましょう。」と受け取り、清水で
洗い手拭で拭いたあとで返してくれる。 その金剛杖を泊まり部屋の中に持ち込み、床の間か部屋の一番良い場所に立てかけるように、言われた。
お杖を洗うのは、金剛杖をお大師様そのものと考え、遍路旅で汚れたに違いないお大師様の足を
洗って差し上げるものだった。
3.死出の旅
江戸時代に盛んになってきた四国遍路では、現代とは比較にならない厳しい歩き旅をするもので、
四国遍路は死出の旅と言われていた。
お大師様の救いを願って遍路に出た、病苦や悩み等を抱えた人もいて、それらの人達の中には遍路途中で行き倒れることも多くあったそうだ。
お遍路さんが遍路途中に亡くなると、その土地の人が、亡くなったお遍路さんを土に埋め、その上に金剛杖を立てたもので、金剛杖は墓標の役割も果たしたと言われている。
4.墓標代わり
五輪塔とは、死者へ対する供養や墓標として造られた石塔で、その形は「5大」を表した5種類の
パ-ツから出来ている。
金剛杖の頭部には、この「5大」が梵字で刻まれており、この部分は大切なものとして、直接手に触れないように錦布で包まれている。
昔の四国遍路では、行き倒れ亡くなったお遍路の金剛杖を、墓標として使っていたそうだ。
5.私の金剛杖
四国あるき遍路を、乗り物を一切使わず 45泊46日の通し で結願出来たのは、金剛杖にいつも
支えられていた気持ちのお蔭と、実感している。
四国遍路を結願し、第88番 大窪寺に金剛杖を納める人たちも居るそうだが、私は記念に家に持ち帰った。
あるガイドブックによると、死出の際に四国遍路に使った金剛杖を棺桶に入れてもらう と、その人は
浄土へ導かれるそうで、私は遺言書の中に書き加える事とした。
〈 菅笠・金剛杖・輪袈裟 〉

第1番 霊山寺横の売店で、金剛杖・白衣(おいづる)・輪袈裟・菅笠・納経帳を買い、身につけると、一見で お遍路 と分かる姿となった。 金剛杖について学んだ事を、ここに書き残しておく。
1.遍路とお遍路
遍路とは、弘法大師(お大師様)が開いた四国八十八ヶ所霊場(札所)を巡拝(巡礼)することで、
巡拝する人が お遍路 と呼ばれ、地元の人は敬意と親しみを込め、お遍路さんと呼ぶ。
2.同行二人(どうぎょうににん)
買った金剛杖と菅笠には、同行二人と書かれており、これは遍路には お大師様がついて一緒に
歩いてくれている事を示し、特に金剛杖はお大師様の分身・化身と教えられた。
この教えは、一人で遍路道を歩いて行く私にとって、心強く感じられた。
お遍路を泊める宿の多くでは、お遍路が宿に辿り着くと「お杖を、洗いましょう。」と受け取り、清水で
洗い手拭で拭いたあとで返してくれる。 その金剛杖を泊まり部屋の中に持ち込み、床の間か部屋の一番良い場所に立てかけるように、言われた。
お杖を洗うのは、金剛杖をお大師様そのものと考え、遍路旅で汚れたに違いないお大師様の足を
洗って差し上げるものだった。
3.死出の旅
江戸時代に盛んになってきた四国遍路では、現代とは比較にならない厳しい歩き旅をするもので、
四国遍路は死出の旅と言われていた。
お大師様の救いを願って遍路に出た、病苦や悩み等を抱えた人もいて、それらの人達の中には遍路途中で行き倒れることも多くあったそうだ。
お遍路さんが遍路途中に亡くなると、その土地の人が、亡くなったお遍路さんを土に埋め、その上に金剛杖を立てたもので、金剛杖は墓標の役割も果たしたと言われている。
4.墓標代わり
五輪塔とは、死者へ対する供養や墓標として造られた石塔で、その形は「5大」を表した5種類の
パ-ツから出来ている。
金剛杖の頭部には、この「5大」が梵字で刻まれており、この部分は大切なものとして、直接手に触れないように錦布で包まれている。
昔の四国遍路では、行き倒れ亡くなったお遍路の金剛杖を、墓標として使っていたそうだ。
5.私の金剛杖
四国あるき遍路を、乗り物を一切使わず 45泊46日の通し で結願出来たのは、金剛杖にいつも
支えられていた気持ちのお蔭と、実感している。
四国遍路を結願し、第88番 大窪寺に金剛杖を納める人たちも居るそうだが、私は記念に家に持ち帰った。
あるガイドブックによると、死出の際に四国遍路に使った金剛杖を棺桶に入れてもらう と、その人は
浄土へ導かれるそうで、私は遺言書の中に書き加える事とした。
〈 菅笠・金剛杖・輪袈裟 〉